蒸気圧について説明していきたいと思います。
蒸気圧=蒸気+圧力
蒸気の圧力ですね。
蒸気に圧力があるの?と思われる方もいるかもしれませんが、
実はあるんです。【ここでは、蒸気=気体として扱います。】
こういった風に、 科学には目に見えない力が働いています。
1、蒸気圧とは
気化した固体、液体の圧力のこと。
一定の温度においては、固体や液体から気化して生じる
蒸気圧はある上限までしか到達しない。
この上限を飽和蒸気圧とよぶ。
 |
| ↑それぞれの温度における蒸気圧曲線 |
飽和蒸気圧は、物質の種類(相)と温度によって定まる。
同一温度では沸点の低い物質のほうが(飽和蒸気圧)が大きいことになる。
同一物質では温度が高いほど大きい。
ときには、飽和蒸気圧あるいは
飽和水蒸気圧のことを単に蒸気圧といっている場合もあるから
注意を要する(むしろこのほうが多いかもしれない)。
[山崎 昶]
2、飽和蒸気圧
したがって、高山の頂上などのように大気圧の低い所では、
地上よりも低温で沸騰が始まる。
これを逆用して、ポンプなどで排気を行って減圧すると、
ずっと低温で沸騰させることができる。
水流ポンプ(アスピレーター)などを用いて実験室でよく行われるが、
これは正確には減圧蒸留であるけれども、よく真空蒸留という。
[山崎 昶]
3、気象
水蒸気張力(略して水張)ともいう。
一般に空気中には水蒸気が含まれており、
気圧は湿潤空気の圧力で、乾燥空気の圧力と水蒸気の圧力の和である。
蒸気圧も気圧と同様にヘクトパスカル[p] の単位で表す。
蒸気圧は、通常の気象観測では、通風乾湿計による測定か、
または露点湿度の測定の結果から求められる。
蒸気圧は存在する水蒸気量によって決まるので、
ある容積の空気中に含まれる水蒸気量を蒸気圧で表示することもある。
水蒸気は空気とよく混合するので、水蒸気の温度のかわりに
気温を用いて差し支えない。
蒸気圧(e )は、厳密には、水蒸気圧のモル率(N v )と
湿潤空気の圧力(p )の積として次式で定義される。
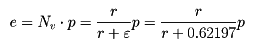
ここに、rは混合比とよばれるもので、
乾燥空気の質量に対する水蒸気の質量の比として表される。
また、εは乾燥空気の分子量に対する水蒸気の分子量の比である。
さらに、蒸気圧(e )、湿度(T )と容積(V )との間には
次の関係が成立する。
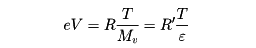
ただし、R は普遍気体定数、R ′は乾燥空気の比気体定数、
M v は水蒸気の分子量である。
大気中の水蒸気は高さとともに減少し、
単位断面積の気柱に含まれる水蒸気量の大部分は対流圏の中にあり、
その大半は高さ3キロメートルの下層部分に含まれている。
[股野宏志]
リンク

コメント
コメントを投稿